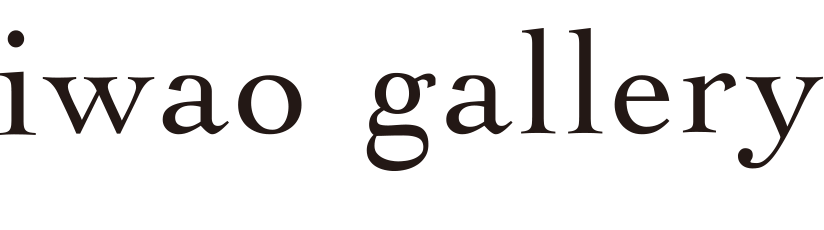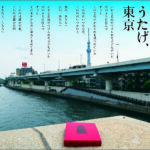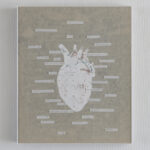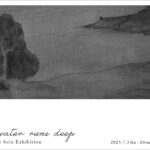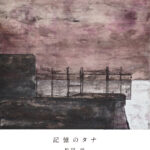『歌は待っている 風と土と「ひとひのうた」と』
刊行記念イベント「夏のうたげ、東京」
2025/8/16(sat),17(sun)
小金沢智編著『歌は待っている 風と土と「ひとひのうた」と』刊行記念イベント 「夏のうたげ、東京」 会期:2025年8月16日(土)12時−20時、17日(日)11時−17時 観覧:無料[投げ銭制]/予約不要 —————————— 夏のうたげ、東京 ここ=iwao gallery(東京都台東区蔵前)は、磯辺加代子さんが2019年11月にオープンしたギャラリーです。その名称は、亡くなられたお父さまの名前「巖」(いわお)から。もともとは、創業97年、三代続く玩具問屋の倉庫だったと聞きます。 はじめて僕が訪れたのは、2022年2月、詩人の管啓次郎さんと写真家の吉江淳さんの展覧会のときでした。年末に父を亡くしたばかりの僕は、父の葬儀の1日を吉江さんに写していただいた写真集を制作中で、見本を持って展覧会の朗読会を訪ねたのでした。すると、磯辺さんは、僕が発表するつもりもなく私家版として制作していた写真集『flows』に興味を持たれ、よかったらここで写真集を見る機会をつくりませんかと提案してくださったのです。後日、「『flows』を見る/読む」と題して行った2022年8月19日、20日の企画は、イベント(トーク:小金沢智、平野篤史、吉江淳、ライブ:前野健太)も含め、僕にとって忘れ難い時間になりました。 あれから三年が経ち、iwao galleryで再びこのような機会をいただきました。「夏のうたげ、東京」は、僕が五月に発売した編著『歌は待っている 風と土と「ひとひのうた」と』(モ・クシュラ)の刊行記念イベントとして、「うたげ」をテーマに、展示、トーク、販売を行う場です。 東北芸術工科大学主催の「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2024」(蔵王温泉、東北芸術工科大学)で行った、周遊型展覧会「ひとひのうた」のドキュメントとして制作をはじめたこの本は、次第に、「うた」を大きな柱とする一冊になっていきました。そして、今回のイベントの名称に掲げている「うたげ」とは、詩人、評論家の大岡信の『うたげと孤心』(1978年)から。大岡は『うたげと孤心』で、優れた作品が生まれるためには、さまざまな分野の創作が同時に行われる「うたげ」の場と、作家の徹底的な「孤心」が必要なのだと述べています。僕は、この二重性に強く惹かれました。今回の機会は、本からの展開として、「うたげ」という場を僕なりにつくってみることにほかなりません。 空間には、吉江淳さんによる本の表紙に使わせていただいた写真《蔵王02》(2024年)、岡安賢一さん撮影・編集による「ひとひのうた」記録映像、出品作家の一人であった大和由佳さんの蔵王の土地の記憶にふれる作品《VINELAND -1/10,000模型》(2024年)の蔵前バージョン。そして、蔵王温泉の南無阿弥陀仏碑をモチーフに、岡澤慶秀さんの本書のための作字をともなった、岡本健+さんの表紙のデザインが(南無阿弥陀仏碑の原寸大で)皆さまをお迎えします。僕は、前野健太さん命名による「展覧歌」(てんらんか)の二作目として、この蔵前という場所のこと、ここで生きている人、生きていた人たちのことなどを想像しながら、「蔵前」をつくりました。そして、2日間、たくさんのゲストの皆さまと、僕がホストとなって、いろいろなお話をさせていただきます。ぜひ、お越しの方も、よろしかったら混ざってください。 初日は、生者と死者が再び出合う、お盆の最終日(8月16日)。流れゆく時間のいっときを、ここにいる皆さまと過ごすことができたらと思い、あちらとこちらのきわ——隅田川の気配を漂わせるiwao ga…